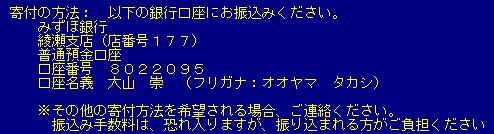�T�v
�{�e�ł́A���n�ŕ��߂����ɔ�������ŋ��ɂ��āA�[�Ŏ҂̎��s���Ƃ������_���琮������B�ŋ���[�߂Ȃ��Ă͂����Ȃ��l�X�̗��ꂩ��̋c�_�͂���܂ő�������Ă������A�ł�����g�D�̗���A���n����Â���g�D�̗��ꂩ����l�@���A���ɊO��n�����o��ɂ����ꍇ�ɂ́A�ǂ̂悤�Ȗ�肪�N���邩����������B�C�O�̋��n�̐Ő��A���n�ȊO�̃M�����u���Ⓤ���ɑ���ŋ��ȂǂƂ���r����B�܂��A���n�̐ŋ��͐\���R�ꂪ�o���Ȃ����߂̎�@���A�������J����Ă��܂��Ă���B�{���A�Ő����l����Ƃ��ɕK�v�ł���������̎��_��������_�A���P�����������B���n�̐Ő��͌��������K�v�ł���ƕM�҂������Ă��邪�A�s�����ȐŐ������߂�ׂ��Ƃ������Ƃ��������A���v�̃v���Z�X�̈�i�K�Ƃ��āA�܂��͊O��n�����o��ɂ��Ă݂Ă͂ǂ����Ǝ咣�������B�O��n�����́A��葽�p�I�Ŋ����ȋc�_���K�v�ł���A�{�e���c�_�̈ꏕ�ɂȂ邱�Ƃ����҂���B
Keywords: ���n�A �Ő��A �O��n���A�ł̌������A�\���R��
�P�@�͂��߂�
�������̑i�ׂ��N���Ă��邱�Ƃ���킩��悤�ɁA���n�Ɋւ���ŋ��ɂ��ẮA���т��ѕ���A���̓s�x�A�[�Ŏ҂̎��_����A�Ő����Ó��Ȃ̂��Ƃ�������N������Ă����B
�{�e�ł́A�[�Ŏ҂̕����s���ɂ��āA�S���グ�A�����̉�����ɂ��āA���p�I�Ȏ��_��������\������������B
���n�̐Ő��ɂ��ẮA�O��n���̎�舵�����肪���ڂ��ꂪ�����ƕM�҂͊����Ă���B�������ɁA���{�d�ŗ��_�w�� (2012)�ɂ��A�W�F���g�͑d�łɂ��Ē~������x�����ׂ��Ő������͎x�����Ȃ��ƌ����Ă���B���x���}�C�i�X�ɂȂ��Ă���l�������������Ƃ����̂́A���Ȃ�⍓�Ȉ�ۂ�����B�������A�������鑤�̗��ꂩ�炷��ƁA�}�C�i�X�����璥�����Ȃ��Ƃ������[���͂Ȃ��Ȃ����ɂ������낤�B���ہA�������H���T�[�`(2024)�ɂ��A�Ԏ��@�l������65%�ł���B�ߐł̂��߂ɁA�����ė��v���o���Ȃ��悤�ɂ��Ă����Ƃ�����悤�ł���B���n�̐ŋ��̃j���[�X�ł́A�����߂���Ɋ����邱�Ƃ����邪�A�������A�������闧��Ȃ�A�Ԏ��ł������ł���d�|���͕K�v�Ȃ̂�������Ȃ��B�܂��A�������啝�Ɍ������l����A�O�N�̏����ɉ����Ďx������ׂ��ŋ�������ꍇ��A����������̂�����ȕs���Y�⊔�𑊑����āA���z�̑����ł������Ȃ��Ȃ�ꍇ�Ȃǂł��A�[�Ŏ҂̎�������������l�����āA���Ƃ���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�������鑤�͗⍓�A���Ƃ������ᔻ���C�ɂ��Ă�����A�d���ɂȂ�Ȃ����낤�B�ނ��낱���������ᔻ�ɂ͊����ׂ���������Ȃ��B
������������Ɩ��Ȃ̂́A�����̔[�Ŏ҂��\�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ɁA�\���R��̏�ԂɂȂ��Ă��邱�Ƃł���ƕM�҂͊����Ă���B�Z����������\���R����w�E���ꂽ�Ƃ��A�������Ă����ΐ\���R����w�E����邱�Ƃ͂Ȃ����낤�Ƃ���������Ă��āA�s�������͔ے�ł��Ȃ��B�r���E�Q�C�c�́A�l���͕s�����ł���Ɋ����ƌ����Ă���B�������A�d�łɂ͎O�����i�����A�����A�ȑf�j�����邵�A���@�ɂ͖@�̉��̕����̌���������B�Ⴆ�A�C���^�[�l�b�g�ɂ��w���ƌ����ɂ��w���œK�p�������łȂ�(�����w���Ȃ略�߂��؋������͎̂�����s�\�����A�C���^�[�l�b�g�w���Ȃ�؋������̂��\�ł���ƌ����Ă���)�̂́A�����̑O����������Ă���ƕM�҂͊����Ă���B�V���E�v���d�Ő��x�͔[�Ŏ҂������ƔF�߂���̂łȂ���Ȃ�Ȃ��ƌ����Ă���B�Ⴆ�Α����ŁE���^�łɂ��Ă݂�A�C�O�ő��^����Ƃ���������������������A�����������܂����B�@�l�łɂ��Ă��A���v���o�����Ɋ��p����Ă��������ی����K������A����������������߂��ƕ]�����Ă悢���낤�B�������A���n�ɂ��ẮA�ꕔ�̔n���̍��z���߂̏������Œ����擾�ł���悤�ɂȂ������x�̑Ή���������Ă��Ȃ��B�������A����̓C���^�[�l�b�g�w�����O��̑Ή��ł���A�����⓽�����̂���J�[�h�Ȃǂł̔n���w���ɂ͓K�p����Ă��炸�A�����ɂ��n���w���œI���Ȃǂ�h��ɍs�킸�A���X���Ă���A�قڐ\���R����w�E����Ȃ��ł���Ɖ��߂ł��Ă��܂��ł���B�C���^�[�l�b�g�w���҂��炷��A�K�p�̕s�������͔ۂ߂Ȃ����낤�B
�������̗��p�҂̕����A�܂Ƃ��ɐŋ���[�߂Ă���l���������Ƃ������n�̐Ő���ς�����@�����邩�A�łɊւ��鎑�i���������A���Ƃł͂Ȃ����ꂩ��A�l�@���Ă����B
�O��n�����o��ɂ��Ȃ����Ƃ��ŏI�I�ȖڕW�ɂ��ׂ����ƕM�҂��v���Ă���B�������A������X�g���[�g�ɑi�����Ƃ���ŁA����܂ł̌o�܂�����ƁA�������Ɍq����̂��^�킵���Ǝv���Ă���B���݂̐Ő��͖{������ׂ��������������Ă���Ƃ������Ƃ��������A�����������@���������ׂ��Ǝ咣�������B�������A�����Ȃ�ł�[�߂Ȃ��Ă͂����Ȃ��n���w���ґS�����[�ł���悤�Ȏd�g�݂���낤�Ƃ���ƁA�卬������̂��e�Ղɑz���ł���B�]���āA�܂��͊O��n�����o��ɂ��Ȃ��ŁA�����ȘR��̂Ȃ�������ڎw���ׂ��łȂ����ƍŏI�I�ɕM�҂͎咣�������B
�Q�@�O��n�����o��ɂ��邱�Ƃ̓���ɑ���s��
���Œ�(2018)�̃E�F�u�T�C�g�ɂ��A�O��n�����o��ɂ��邽�߂̋�̗�Ƃ��āA
(i)�����I�ɔn�����w������\�t�g�E�F�A�̗��p
(ii)�قڑS���[�X�ւ̓K�p
(iii)�N�Ԃ̎��x���P�O�O�����Ă��邱�Ƃ̋q�ϓI�ȏؖ�
�Ȃǂ��������Ă���B���������ׂĖ������Ȃ��狣�n���y���ނƂ����̂́A���Ȃ����Ǝv����B�����āA�����̏��������Ȃ��n���̍w�����@�����Ă���ꍇ�A�O��n�����o��Ƃ�����
(1) �ŋ��v�Z�̂��߂̎��x
= (���ߋ��z�\���߂̂������n���̍w����p)�̂P�N�Ԃ̑��a
���v�Z���A���ꂪ50���~����ꍇ�́A(1)���ꎞ�����Ƃ��āA���̏����Ȃǂ����������ŋ���[�߂�K�v������B
���n�̕��߂Ɋւ��āA�ŋ���[�߂����Ȃ��̂ł���A(1)��50���~�ɂȂ�O�ɁA���̔N�͔n���w������߂Ȃ��Ă͂����Ȃ��B
�}1�͕M�҂�2025�N�N�n����L�^���n�߂����n�̎��x�̐��ڂł���B�@�d�܃��[�X�ɂ����Ēa�����Ɋ֘A�t�����n���A�e�q�E�Z��R��̘g�A�E���C�h�ȂǁA�Q�`�R��~���x�w�������B�A���̑���100�~�����P�Ԑl�C�̒P���܂��͕����̔n�����w�������B�ڍׂ͑�R(2025a)���Q�Ƃ��ꂽ�����A�@�̍w�����@�͓I�����Ă��������100%�ɂȂ�Ȃ��g���K�~��������������B�㑤�̃O���t�͐ŋ��v�Z�̂��߂̎��x(1)�A�܂�O��n�����o��Ƃ��Ȃ��������̎��x�ŁA�ǂ�ȂɘA�s���Ă����邱�Ƃ͂Ȃ��A�P���ɑ������Ă��邱�Ƃ��킩��B�����̃O���t�͊O��n�����v�サ�����ۂ̎��x�ŁA�E������̌X�������A100%�̉�����̃��[�X�����������ɉ��Ă��邱�Ƃ��킩��B92���[�X�ځi��ˋL�O�j�ŎO�A���Ȃnjv2��5��~�̕����߂����������B���̃O���t������ƁA���ۂɂ͂���Ȃɗ�������ł���̂ɁA�ŋ��v�Z�̍ۂɂ͂���Ȃɖׂ��Ă���Ɖ��߂���Ă��܂��̂��ƈ��R�Ƃ��Ă��܂��B7��27�����_(108���[�X�ōw��)��(1)�̒l��61,320�~�ɂȂ��Ă���B�������A���ۂɂ�157,700�~�w������69,220�~�̕��߂����Ă��Ȃ��B�n���͑S��100�~�̍w���ŁA77��̓I�����������B������͖�43.9%�ł���B���̂܂܂̃y�[�X�ł���ΗL�n�L�O���I����Ă�(1)��50���~�ɂȂ�Ȃ����낤����A���n�̐ŋ��Ɋւ��Ă͊m��\�������Ȃ��Ă悢���ƂɂȂ邾�낤�B�������A50���~�����ɒ����Ă��܂��A���������ۂ̉������44%���x�������Ƃ�����A�Ȃ��ׂ����Ă��Ȃ��̂ɐŋ���[�߂�̂��A�������ʂɖI�Ǝv���Ă��܂����Ƃ��낤�B
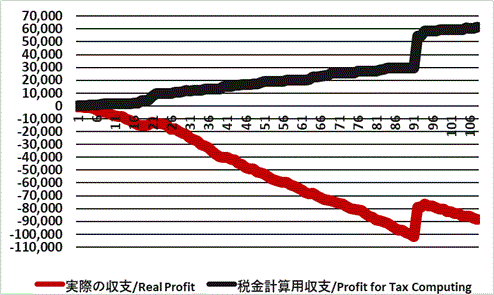 �}1 �M�҂̋��n�̎��x
�}1 �M�҂̋��n�̎��x�悭���n�̉�����͕��ς���ƁA���ߗ��Ɠ����x��70%����80%�ƌ�����B���ɂ���l�̉������70%�ŁA����12����x�I������Ɖ��肵�悤�B (1)��50���~���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�ꂩ���ł�(1)�̒l��50��12����4.2���~�ɂȂ�B�����70%�̉�����̐l�Ȃ猎��6.2���~�q����4.3���~��������A��1.9���~�̑������o���Ă���Ƃ����v�Z�ɂȂ�B���n���D�Ƃ̒��ɂ͂������������������āA��葽���̗��v���o���Ă��܂��Ă���l���������݂���̂ł͂Ȃ����낤���B��̓I�Ȑ�����M�҂͎����Ă��Ȃ����A�S���[�X�ɐ���~�������Ă���l��P���[�X�ɐ����~�g���l����O�n����Ȃǂł悭��������B�������I�����A������A���ߋ��z�̕��ςȂǂ͐l���ꂼ��Ȃ̂ŁA��L�̘b�������āA�ŋ���Ȃ��Ƃ����Ȃ��l���������݂��邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����A�������n�Ƀn�}���Ă��܂��A�����ɐŋ���Ȃ��Ă͂����Ȃ����v���o���Ă��܂��Ƃ������Ƃ͂킩���Ă��������邾�낤�B�t�ɁA���̐Ő����v���X�ɉ��߂��悤�Ƃ���Ȃ�A�ꂩ���ɊO��n�����o��ɂ��Ȃ��Ŗ�4.2���~���闘�v���o�Ă��܂�����A���ۂ̗��v���Ԏ��ł������ł����̌��͔n���w������߂�A��������M�����u���ˑ��ǂɂȂ�Ȃ��ōςނƌ����Ă���̂�������Ȃ��B���ۂɐԎ��̐l�ɂƂ��Ă͓K�ȏ����ɂȂ邩������Ȃ��B�������͐������Ȃ��A��������Ⴏ��Ώ�L�ł͈ˑ��ǂ̑�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�N��50���~�̗��v�Ƃ͊W�Ȃ��A���Ɏg���鋣�n�̋��z�A�����̏����l���ƂɎ��Y������f�ޗ��Ƃ��Č��߂�̂��Ó��ł���B���邢�̓M�����u���ˑ��Ǒ�A�M�����u�����N�����Ă���ƌ�����ƍ߂�h�����߂ɂ́A�e��J�[�h�Ɠ��l�ɗ��p���x�z�Ȃǂ�ݒ肷�ׂ��Ȃ̂�������Ȃ��B
�R�@�ŋ��̂�����Ȃ��M�����u���⊔�������ȂǂƂ̕s������
����T�b�J�[�����ł́A�傫�ȕ��߂��Ƃ��Ă��A�ŋ��͔������Ȃ��B����Ȃ̂ɁA���n�ł͐ŋ���Ȃ��Ă͂����Ȃ��B����͍w�����̍T���������n�ł͏��������߂ł���ƌ����Ă���B�������A���n���D�Ƃ���݂�Ɣ[�������Ȃ����Ƃł���B�T���������̃M�����u���ɔ�ׂď������Ƃ͂����A�w������20����30%���T������Ă��܂��Ă��āA��10%�̍��ɔ[�t����[�߂Ă���B�����̗��v�������������ɂ��ŋ���[�߂�͓̂�d�ېłł���Ǝw�E������Ƃ�����B
������d�ېłƂ����ᔻ������悤�Ƃ���Ȃ�A�܂����ɔ[�t������߂邱�Ƃ��l������B��������T������10%���x�ɂȂ�A�I�����̕��ߋ��z���傫���Ȃ�B�������A�m��\���ɂ��Ŋz������Ɠ����x�ł���A�Ŏ��������Ă��܂����ƂɂȂ�B�]�k�����A�T������10%�ƒႢ�V���K�|�[���̋��n��́A�T�����̒Ⴓ�����R�ł͂Ȃ��ƌ����Ă��邪�A������Ă��܂����B
�t�Ɋm��\�������Ȃ��ł����悤�ɁA�w�����̍��ɔ[�t���݂̂ŐŎ��悤�Ƃ���l����������B���ہA���n�i�r(2024)�ɂ��A50%�̍T����(�Ҍ���)�̍�������B���ɕ��Ɠ����x��50%���x�ɂ��Ă��܂��ƕ��߂��P���v�Z�ŗႦ�ΒP�������Ȃ�62.5%���x�i=50��80�j�ɂȂ��Ă��܂��B�������ɂ���قǕ��߂������Ă��܂��Ƌ��n���D�Ƃ�����Ă��܂����낤�B�M�҂́A�I�b�Y�̏������l�C�n�����郌�[�X�ɂ����āA�I�b�Y��p���ĉ��̎x������
(2) �I�b�Y��p�������̎x����=���ߗ����I�b�Y
(���[�҂̍w�����z�͓����łȂ����A�I�b�Y���Ⴂ���Ƃ������ė\�z�̖{���Ƃ͈قȂ�l�C�n�łȂ��n�����w������ꍇ�����邽�߁A�I���␢�_�����̎x�����Ƃ͈Ӗ������͈قȂ�B)
�Ƃ��Čv�Z���A���̔n�����������邩�m�F���Ċy���ނ��Ƃ�����B���{�̒P���̏ꍇ�A���ߗ���80%�Ȃ̂ŁA�I�b�Y��1.6�{�̏ꍇ�A(2)��50%�ɂȂ�B2.4�{�̏ꍇ�A33%�ɂȂ�B���v�f�[�^�͌��J����Ă��邪�A1.6�{�Ƃ��Ȃ�A�������m���͍����Ǝv���A�����邱�Ƃ������Ƃ�����ۂ�M�҂͎����Ă���B100�~�q����160�~�̕��߂�����ƍl����̂ɂ́A�Ó��ȃ��X�N���ȂƎv���Ă���B�������A�T������50%(���ߗ���50%)�ɂ��Ă��܂��ƁA����1.6�{�̃I�b�Y�������n�̃I�b�Y��1.0�{�Ƃ������ƂɂȂ�B2.4�{�̔n�̃I�b�Y��1.5�{�ɂȂ��Ă��܂��B���X�N�ɑ��āA���߂����|�I�ɏ������Ƃ�����ۂ������Ă��܂��B��Â��鑤����݂Ă��A���ւ̂悤�ɁA�P���A�����͔������Ȃ����������Ƃ����l���Ɏ��邩������Ȃ��B�������A���C�h��n�A�Ȃǂł����������ߊz������A�y���݂͌���A���D�Ƃ�����Ă��܂����낤�B�C�M���X�̘b�ɂȂ邪�ARacing Post, Peter Scargill (2025)�ɂ��A�����ɂ����čT�����̈����グ���c�_����Ă��邪�A�W�c�̂͋��n�ƊE�ւ̉e���ɂ��ċ������O�������Ă���B���̂悤�ɁA�ŏ����略�ߗ�����������A�s���͂Ȃ����낤���A���ߗ���������Ƃ����̂́A�e�����傫���Ɨ\�z�����B
�����������n�Ȃǂ̃M�����u���ƕ��Ȃǂ̃M�����u���̍T���������킹�邱�Ƃ̈Ӗ����c�_��������������������Ȃ��B�l�Ԃ̏ꍇ�AA�����B����̎�舵���ɍ�������A���ʂƂ��s�����Ƃ����b�ɂȂ邪�A�M�����u��A�ƃM�����u��B�̍T�������Ⴄ�Ƃ��ŏI�I�ȍw���҂̕��S���̂悤�Ȃ��̂��Ⴄ�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ����ɂȂ肤��̂��낤���B���Ȃ݂ɁA�������T�C�g(2025)�ɂ��A�ߘa6�N�x�̔���͖�8,000���~�ŁA��3,000���~���������Ɠ��Ɏg���Ă���B����AJRA(2025)�ɂ��A��3,300���~����ꎟ���ɔ[�t���ɂȂ��Ă���B���ɔ[�t���̊z�ł����A�قړ����ɂȂ��Ă���킯�ŁA�N��50���~�ȏ�̕��߂��������l����̐Ŏ������Z���Ȃ��Ă����ȏ�̍v�����Љ�ɑ��čs���Ă���ƕ]���ł���Ǝv���B�M�҂́A�N��50���~�̗��v���o���Ċm��\��������͖̂ʓ|�����A���ɐŊz���x��������Ȋz�ɂȂ��Ă��܂��ƌ����ȂƎv���A50���ɒB���Ȃ��悤�ɔn���w�����T���Ă���B�������A�N��50���̐������Ȃ���A�����Ƌ��n�ɂ������g�������Ǝv���Ă���B�M�҂Ɠ����悤�ȍl���̐l���ǂꂾ�����邩�킩��Ȃ����A���n�l���𑝂₷�A��l������̍w�����z�𑝂₵�č��ɔ[�t���𑝂₷�Ƃ���������\���c�_�ɒl����̂ł͂Ȃ����낤���B
���n���M�����u���łȂ������Ƃ��čl���Ă���l�̏ꍇ�A�������100%���z���Ă��邱�Ƃ��q�ϓI�ɏؖ��ł��Ȃ��ƊO��n�����o��Ƃ��ĔF�߂Ă��炦�Ȃ��Ƃ����̂��s���ɂȂ�B���������̏ꍇ�A���^�����z�ɂ������͈قȂ邪�A�������o���ꍇ���܂߂ė��v�����ȉ��̏ꍇ�A�m��\�����s�v�ɂȂ��Ă���B���{���ۏ���Ă��Ȃ������͐���������̂ɁA���n�ɑ��Ă̂݁A���������������Ȃ���Γ����Ƃ��ĔF�߂Ȃ��Ƃ����̂́A�f���ɔ[������̂�������낤�B
�����Ƃ��ċ��n���l���Ă��鎞�ɁA�O��n�����l�����Ȃ��Ƃ����̂����\�ł���B�����ɂ́A�������i���ɉ^�p���āA��������ɂ��܂������Ȃ������Ƃ��Ă��A�������s�������̑��������ߍ��킹�ė��v�ݏo���Ƃ����l����������B���n�������悤�Ȃ��̂��ƕM�҂͍l���Ă���B�����炭������x�̌o���������Ă��鋣�n���D�Ƃ̑����́A�O��邱�Ƃ����邪�A�����������ɊO�ꂽ���̑��������Ԃ���A���邢�͏����҉�ł���ƕ������Ă��邩��A�O��Ă����n���p�����Ă���̂ł���B�����Ɠ�����Ȃ��Ă������Ǝv���Ȃ���n���w���𑱂��Ă���l�͂��Ȃ��Ƃ������Ƃ��ؖ��ł��Ȃ����A�����̋��n���D�Ƃ͏�L�̂悤�ȐS���ŋ��n���y����ł���Ǝv���B���̑O���S�ے肷��̂́A���\���Ǝv���B���n�̓M�����u���̒��ł����Ȃ�ٗႾ�Ƃ͎v�����A�n�Ԃ�l�C�����Ƃ̓I�����A����������n�ꖈ�Ɍ��J����Ă���B�R��⒲���t�A�Y��Ȃǂ̐��т���������Ώo�Ă��邱�Ƃ������B�V���ɂ���Ă͗\�z�Ƃ̐��т����J���Ă���B�����̏��͒����I�ȑ����̃��[�X���ʂ����ƂɎZ�o���ꂽ���l�����A�����̔n���w���҂͂����̐��l�ӎ���������Ȃ����A�l���ɓ���Ă��邾�낤�B�܂��A�������g�̐��т��ӎ����Ă��邾�낤�B�����������w�i������̂ɁA�ŋ��v�Z�̎��̂݁A���郌�[�X�œ��������̂́A���̑O�̃��[�X�̊O��Ƃ͖��W�ł���Ǝ咣����̂́A�s���̗ǂ��f�[�^�݂̂��o���Ă���ƌ����č����x���Ȃ����낤�B
�܂��A�����̔n���W�����n���̃{�b�N�X�A�����̍w������S�ʂ�A�S���w�����I���n���݂̂��o��ɂȂ�Ƃ����̂́A�n���w���҂̈Ӑ}��g�܂Ȃ��Ό��ɖ������Ή��ł���B�S���w���̏ꍇ�́A�K���ǂꂩ��������Ƃ������Ƃ����Ĕ����Ă���킯�����A�{�b�N�X�◬���̍w�����@���ǂꂩ�͓����邾�낤�Ɗ��҂��čw�����Ă���킯�ł���A�����������w�����ɂ́A�O��n�����o��ɂ��ׂ����ƕM�҂͎v���B
�o��Ƃ��ĔF�߂��Ȃ����̘b�Ō����A�M�҂̓X�[�c��C�V���c�ɂ��Ă��s���������Ă���B�����Ɖ��Ȃ����ɂ͉�Ђ�T�V���c�Œʂ��Ă��鎄�ɂƂ��āA�X�[�c��C�V���c�͓����납�璅����̂łȂ��A�Ɩ��ł������Ȃ����ʂȈߑ��ł���B�w����N���[�j���O��p�͕K�v�o��ł���Ǝ咣���������A�ŗ��m�������Ȃ��̂ŁA�]�킴��Ȃ��B�l�ԂȂ�H���͕K�v�Ȃ̂ɁA�����Ƃ̍��e��̈��H��ȂǑS�z�o��ɂȂ邱�ƂƔ�r����ƁA��������[�����邱�Ƃ͉i���ɖ����ȋC�����Ă���B�����͌����Ă��A�X�[�c�A���C�V���c�̈����ɂ��ẮA�ꕔ�̗�O�������A�S������������舵�����Ă���A���������Ӗ��ł͌������͎���Ă��āA�[�����͂���B
�������鑤�̎��_�ōl���Ă݂�ƁA����̊O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂Ȃ��œ�����Ŋz�́A�ȉ��ŕ\�����Ƃ��ł���B���������ȓǎ҂͐��i����́u�v����Ɂv�Ŏn�܂�i���܂ŃX�L�b�v���Ă������������B
(3) �O��n�����o��ɂ��Ȃ��ꍇ�̐Ŏ���A�~B�~C
A:�l��
�O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂Ȃ��������ɁA�ŋ���[�߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��l�̐l��
�@�@�@B:��l������̐Ŋz�i�P���j�ŋ���[�߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��l�������ׂ��Ŋz�̕���
�@�@�@C:�B����
�ŋ���R��Ȃ������ł��銄��
����A�O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂�ꍇ�ɓ�����Ŋz�́A�ȉ��ŕ\�����Ƃ��ł���B
(4) �O��n�����o��ɂ���ꍇ�̐Ŏ���A�~a�~B�~b�~C�~c
a:�O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂����́A�ŋ���[�߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��l�̐l����A�ɑ���䗦
�@�@ b:�ŋ���[�߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��l�������ׂ��Ŋz�̕��ς�B�ɑ���䗦
�@�@ c:�ŋ���R��Ȃ������ł��銄��(�B����)��C�ɑ���䗦
���̂悤�Ȏ��ŕ\���܂ł��Ȃ��A�킩�肫�������Ƃł͂��邪�A�O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂Ă��܂��ƁA�ŋ���[�߂Ȃ�������Ȃ��l�̐l�������|�I�ɏ������Ȃ��Ă��܂��BA����A�~a�ł���B���x��100%���z���Ă���l���ǂ̒��x����̂��A�M�҂͐��m�Ȑ����������Ă��Ȃ����A�ˉz(2025)�̓A���P�[�g�ɂ�邻�̐��������J���Ă���B���Ȃ菬���������ł���B
�܂��A�O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂�AB����B�~b�ł���B�ǂ̒��x�����Ă��܂��̂��A�M�҂͐������o���Ȃ����A100%�����̐l�����̊O��n�����瓾��ꂽ�ŋ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂́A�������鑤���猩��Α����傫�����낤�Ɛ��@�ł���B
���������āA(4)��(3)�ɂł��邾���߂Â������Ǝv���ƁAc���ł��邾���傫���A���Ȃ��Ƃ��O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂Ȃ������Ƃ����͊m���ɒ�������悤�ɂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��BC��C�~c��ڎw���͓̂��R�Ƃ��āAC�~c��100%��ڎw���āA�ł̌����������߂�ׂ��ł��낤�B
�������A����C�~c��100%�ɂȂ����Ƃ��Ă�A��A�~a�̍��AB��B�~b�̍����Ƃ��ɑ傫���ƕM�҂͗\�z����B
�v����ɁA�O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂�悤�ɂ��Ă��܂��ƁA�ŋ���[�߂�l�����A��l������̔[�t�z�������Ă��܂��B��������ƁA�B�������������āA�\���R����Ȃ����悤�ɂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�������A���ɐ\���R����O�ɂł����Ƃ��Ă��A�Ŏ��͌����Ă��܂����낤�B���������������鑤�̗���Ȃ�A�O��n�����o��ɂ���̂ł���A�\���R����Ȃ����ׂ����S�Ȓ������ł���悤�Ȍ����w���҂��܂߂��S�w�����̎擾�A�O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂Ȃ������Ƃ��Ƃ̍��z�����ɔ[�t���̑��z�A���Ȃ킿�T�����̈����グ���A�����ʂ̍����ɋ��߂Ă��܂����낤�B���������O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂�ꍇ�A�Ŏ�������Ȃ��悤�Ȏd�g�݂��\�z����̂͒��߂�ׂ���������Ȃ��B���ۂ̐������g�������Z�������ł����Ƃ�����A�����I�ɖ������Ƃ������Ƃ��킩�邩������Ȃ��B�����炭��������g�D�������������z���]���ɂȂ���̂��Ǝv���B�����l����Ƃ��̑g�D���������z�����炷�悤�Ȏ��g�݂�ϋɓI�Ɏ����킯���Ȃ��A���̋c�_�͑����Ȃ��Ǝv����B
��������A�O���̑������O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂Ă���̂�����A���{���F�߂�ׂ��Ƃ����ׂ���������Ȃ��B
�S�@�C�O�Ɣ�r�������̕s��
�Ő��͍����Ƃɒ�߂��Ă���͓̂��R�Ȃ̂ŁA��r����Ƃ����͓̂K���łȂ���������Ȃ��B�����������͌����Ă��A���͖ڂɂ��Ă��܂��B����(2013�����2018)�������悤�ɁA�O���ɖڂ�������ƁA�O��n�����o��ɂȂ鍑������B�^���Ȃ�O��n�����o��ɂȂ�̂ɁE�E�E�ȂǂƎv���Ă��܂��͎̂d���̂Ȃ����Ƃƌ����邾�낤�B
���Ȃ݂ɁA����(2023)�͏���ł��O���Ɣ�r���Ă��邪�A����ɂ��Γ��{�̏���ł͐ŗ��Ƃ����Ӗ��ł͏��O���ɔ�ׂč����Ƃ͌����Ȃ��B�܂��A���X(2024)�͏����ł⑊���ł��l�������������S����p���āA���O���Ɣ�r���Ă��邪�A��͂肱�̒l�����{�����ʂɍ����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B����ŁA����(2024)�͑����ł��O���Ɣ�r���Ă���A����ɂ��A�������ɓ��{�̑����ł͕x�T�w�������Ɗ����Ă��܂��͎̂d���Ȃ����x���ƌ����邾�낤�B���ۂɕx�T�w���O���֍s�����Ƃ���������Ƃ����b�͂悭���ɂ���B�O��n�����o��ɂł��Ȃ��̂ł���A�O���֍s�����Ƃ���������Ƃ����l�����邩������Ȃ����A����A�o�Ă��邩������Ȃ��B
�T�@�ŋ���[�߂Ȃ��l���������݂��邱�Ƃւ̕s��
��v�����@(2017)�̂悤�ɁA�ŋ���Ȃ��Ă͂����Ȃ��l����������͂��Ȃ̂ɁA�����Ă��Ȃ��l���������āA���̎��������\����Ă��܂��Ă���Ƃ������Ƃ��A������Ɣ[�ł��Ă���l���猩��ƕs���ɂȂ�B��L���č��z�̕��߂ɂ��Ă͑Ή����Ȃ���Ă���B�������A���̑��ɂ��Ă͑Ή����i��ł���̂��肩�łȂ��B
���v���o���Ă���Ƃ������Ƃ���Ă��܂��Ⴊ�A�����̃E�F�u�T�C�g�⓮��Ŕ��M����Ă���B���̂��Ǝ��́A�ŋ��������Ȃ��Ǝv���Ă���l���������ƁA�l�Ԃ̎コ��\���Ă���Ǝv���B
����͐ŋ���V��������Ă���T�����[�}�����V��������Ȃ��l�����ɑ��ĕ����s�������Ɠ����悤�Ȃ��̂ƌ����邾�낤�B�������A�V�����ł��Ȃ��l���������������Ɣ[�ł��Ă��炤���Ƃ���̖ړI�Ƃ��ĉ��߂ł���A�C���{�C�X���x���������ꂽ�B�O��n�����o��ɂ��邩�ǂ����̖��Ƃ͕ʂɁA�ŋ������̂ł���A�L�������Ɏ��w�͂����ׂ����Ǝv���B�܂��A�������鑤�Ȃ�A���n�̐ŋ������߂̍ۂɈꎞ�I�ɓV�������A�N�Ɉ����A������ׂ��^�C�~���O�ŔN�������A�m��\���̂悤�ɒ�������Ƃ����悤�ȈĂ��l�����邩������Ȃ��B�������M�҂��������A�Ҕ������N���邾�낤�B�������s�������̕��@�ɂ͂Ȃ邾�낤�B
�}1�̘b�ɖ߂��Ă��܂����A�M�҂�2021�N����n�����w������悤�ɂȂ������A2025�N������x��\�v�Z�\�t�g���g���ċL�^����悤�ɂȂ��āA�C�Â����̂́A�����̎��x�Ɋւ���v�����݁A�L���Ƃ����̂͂�����������Ă���Ƃ������Ƃł���B�M�҂̏ꍇ�A�哖���肵���L���͑N���ɒ����c��A�A�s�ɂ��Ă͂����Y��Ă��܂��Ă����B�Ȃ�ƂȂ��n�����w������ƌ����c�������邱�Ƃ̕��������Ȓ��x�̔F���͂��邪�A�����̉�������A���ԂŌ����Ă���悤��70������80���A���������Ƃ��Ă�60�����x�łȂ����ȂƁA�L�^������O�͎v���Ă����B���ꂪ���ۂɂ�44%�Ȃ̂���������ł���B������ł��炻��ȏł���B�O��n�����o��Ƃ��Ȃ����v�̂P�N�Ԃ̍��v�Ƃ��Ȃ�ƋL�^�����Ȃ��Ɣc������̂͋ɂ߂č���Ǝv����B�L�^�����Ȃ���A�̈ӂłȂ��Ă��A�N��50���~�ɒB���Ă��Ȃ��Ǝv���Ă��܂�����A���m�Ȑ�����ł��Ȃ����낤�B���������̏ꍇ�A��������N�Ԏ�������N�n�ɑ����Ă��āA�m��\���Ɋ��p�ł��邪�A���n�̐ŋ��ɂ��Ă�������O�ꂷ��̂ł���A�n���w���҂��n���w�����Ǘ�����g�D�ɂ����̍쐬���`���t����ׂ��ł��낤�B�m��\�������邩���Ȃ������f����͔̂n���w���҂ɔ��f������Ƃ��āA�K�v�����邩�Ȃ�����m�点����x�̂��Ƃ͊W�c�̂ɋ��߂�Ƃ����̂͐��_���낤�B�C���^�[�l�b�g�ɂ��n���w���ł��A��O�n����Ȃǂł̌����₻�̑��ɂ��n���w���ł��A�w���O�ɔF�V�X�e���Ȃǂ��o�R��������x�̃R�X�g�ł���A����Ō�������������Ȃ�����̂ł͂Ȃ����ƕM�҂͎v���Ă��܂��B�������M�҂����n�W�c�̂̎҂ł���A���オ�����邱�Ƃ������Ă�����g�݂Ȃ̂ŖҔ�����̂����B�܂��ARacing Post, Peter Scargill (2025)�ɂ�����悤�ɁA���ߗ���������̂Ɠ��l�ɁA���p�҂̔������悤�Ȏd�g�݂�����A�s���ȃV�X�e���̗��p�ŃM�����u�����s���Ă��܂��l��������Ƃ������O������̂ŁA�T�d�Ȍ������K�v�ł���B
�U�@End Talk
�{�e���������w�i
�{�e�ł́A���n�̐ŋ��ɂ��āA�������̎��_���琮�������B
���������V�X�e���Łu���n�v�A�u�ŋ��v�Ȃǂ̃L�[���[�h�Ő�s������T���Ă݂�ƁA�i�ׂɊւ��邱�ƈȊO�̎Q�l�����������o�Ă��Ȃ������B����������ƁA���Ƃ������e�[�}�Ƃ��Ď�舵���ɂ����������̂�������Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B�������������Ƃ�����A�����͂��ׂăE�F�u�T�C�g��ōs���Ă���B�}���قȂǂł̏��Ђ̒����͈�؍s���Ă��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA�s�\���Ȓ��������ł���Ǝ��o���Ă���B�������A�l�I�ɒm�肽�����͂�����x���Ă���̂ŁA���̖������������Ă���B
�܂��A�M�҂͐ŗ��m�ł��Ȃ����ٌ�m�ł��Ȃ��B�������������I�Ȓm�����Ȃ��܂܁A�{�e�������Ă���̂ŁA�{���͍l�����ׂ������������Ă��邩������Ȃ��B�������A�f�l�Ȃ�ɑf�p�ȋ^����܂Ƃ߂����Ƃɂ́A�|�����̒m�炸�Ȃ�ł͂̌����A���Ƃɂ͌��������Ȃ��������邩������Ȃ��Ɗ��҂��Ă���B
�����܂ŁA�s�����ȐŐ����ǂ��ɂ��������ȂǂƂ������������Ƃ������Ă�����������Ȃ��B�������A���͖{�e���������Ƃ����߂����R�́A����ȂɖJ�߂�ꂽ���R�ł͂Ȃ��B���������ǎキ�āA�����ŗD��Ő����Ă���B�M�҂������Ƃ��Ĕn���w����{�i�I�ɍs�������Ǝv���Ă���B���̎��Ɉ�ԕ|���̂́A�\���R����w�E����Ă��܂����Ƃł���B��������͏���Ȏ咣�����鏀���͑����ɂł��Ă���̂������v�Ƃ������n�t�����Ȃ��B�n���̐ŋ��Ɋւ���c�_�������ɂȂ��āA���̌��ʁA���n�𓊎��Ƃ��ĔF�߂�������傫���ɘa����邱�Ƃ����҂��Ă���Ƃ����̂��M�҂̖{���Ȃ̂ł���B
�M�҂�2025�N3����Ohyama(2025b)�����J�����B2025�N8����9���A�x���Ƃ�10���ɂ́AOhyama(2025c)�����J�������Ǝv���Ă���B����2025c�̘_���ł�Doubling(�}�[�`���Q�[���@�A�{�X�Q�[��)�����p�����K���@���c�_���Ă���B���ۂ̃��[�X�f�[�^�ł͂Ȃ��V�~�����[�V�������ł̓��X�N�������������܂܁A105�`110�����x�̉�����������錩�ʂ��ł���B�������A���������̋�_�łȂ��A���Љ�ňӖ��̂�����̂ł���Ǝ������߂ɂ́A�ǂ����Ă����ۂ̋��n�Ŏ��؎��������Ȃ��Ă͂����Ȃ��ƕM�҂͎v���Ă���B�����A���̘_���Ŏ����Ă����@�͍��Œ��̎����O��n�����o��ɂ��邽�߂̃K�C�h���C�������Ă��Ȃ��B���Ȃ킿�A�\�t�g���g���Ĕn���������ōw������킯�ł��Ȃ����A�قƂ�ǂ��ׂẴ��[�X�Ŕn�����w������킯�ł��Ȃ��B���炭�͔N��50���~�̗��v���o���Ȃ��͈͂Ō����s���\�肾���A�����ꂻ������z�ł̌����������ƍl���Ă���B�������A�O��n�����o��ɂ��邩�ǂ����ŗ��v�͑傫���ς���Ă��܂��B�M�҂�2025c�̎�@�𓊎��Ƃ��čl���Ă���̂ŁA�u������������@�Ȃ�͂���n�����o��Ƃ��Ă݂Ƃ߂Ă���܂����H�v�ƐŖ����ɑ��k���Ă݂����A���Œ��̃K�C�h���C���ȏ�̂��Ƃ͐\���グ���Ȃ��Ƃ̉������B�����̐ŗ��m�A�ٌ�m�ɁA�Ŗ������Ŏw�E����O�ɁA���̎�@�Ȃ�O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂Ă��炦�邩���n�t�������炤�悤�Ȃ��Ƃ͉\���₢���킹�����Ă݂����A������̐ŗ��m�A�ٌ�m���A���_�Ƃ��Ă͎��ށA�܂��͘b�������Ă���Ȃ������B�i�ׂ�������ɂ�āA�O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂�������ω����Ă����\�������邪�A���Ƃ��ẮA������50���~���闘�v���o���O�ɁA���Y��@�̍w�����@�ł���A�O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂�Ƃ������_�����Ǝv���Ă������A���̌��_��͓̂�����ł���B�O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂�ׂ����Ǝ����͎v���Ă���̂ŁA���̂悤�ɐ\�����A�\���R����w�E����邩�A�M�����u�����邱�ƂɂȂ邩������Ȃ��B��c(2015)�͍ō��ٕ���27�N3��10����O���@�씻���ɂ���Ĕ������ꂽ�v�������I�m�ɉ��߂��邽�߂ɁA�ǂ̂悤�ȏꍇ�ɕ��߂��ꎞ�����ł͂Ȃ��G�����ƂȂ�̂����_�I�Ȍ������s���Ă���B�������A���̔����́A����n���w���҂̔n���w�����@�ɑ��ĎG�����Ƃ��Ĉ������Ƃ�F�߂Ă���̂ɉ߂����A���ׂĂ̔n���w���҂̍w�����@�ɂ��ẮA�����ł͘_���Ă��Ȃ��B���ɂ͂����v����B�������A���Œ��̃K�C�h���C���͂��̔��������ƂɎG�����Ƃ��ĔF�߂���������肵�Ă���B���̍w���҂̕��@���K�C�h���C���ɓK�����Ă��邩��Ƃ����āA����ȊO�̔n���w�����@�̓K�C�h���C���ɑ����ĂȂ��̂ŁA�����Ƃ��Ă͔F�߂܂���Ƃ����̂́A�_���̔����Ƃ���ς�v���Ă��܂��B�����̑O��ɂ͑吔�̖@���ɂ��A��ʓI�ȍw�����@�ł͉���������ߗ��Ɠ����x�Ɏ�������Ƃ����������g���Ă��邪�A���Ȃ��Ƃ�Ohyama(2025b, 2025c)�ň����Ă���w�����@�͑吔�̖@���̉e�����ɗ͎Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɁA�S���[�X�ɓq����̂ł͂Ȃ��A90%���x�̃��[�X�̓X�L�b�v���邱�Ƃ��������Ă���B�吔�̖@���͎��s�������Ȃ�Η��_�I�Ȋ��Ғl�Ɏ�������Ƃ������̂Ȃ̂ŁA���s�����Ȃ����Ă������̉e�����ɂ����Ȃ邱�Ƃ������Ƃ͂킩���Ă��������邾�낤�B2025c�ň������@�́A�ȒP�ɂ����ƁA(��)�����Ƃ��������邱�Ƃ̕����������Ƃ͂킩���Ă���̂ŁA���x���v���X�ɂȂ����炻�̓��͉����[�X�c���Ă��Ă��q����̂��I������B(��)��ꃌ�[�X����q����̂ł͂Ȃ��A�I�����̍����P�Ԑl�C�̃I�b�Y���Ⴂ���[�X�łP�Ԑl�C�ɓq���邱�Ƃ���n�߂�B(��)������������A��͂�I�����̍����P�Ԑl�C��2.0�{�ȏ�̃��[�X�ɓq����B(��)������������玟��3.0�{�ȏ��1�Ԑl�C�ɓq����B(��)�������������1�Ԑl�C��2�Ԑl�C�ɓq����B(��)����ł����x������������ŏI��i�Ƃ��ĂP�Ԑl�C��Doubling��K�p(Doubling�̓K�p���ɂ͏����ʓ|�Ȏ����g�p)����[�Ƃ������̂ł���B
�吔�̖@���ւ̑Ή��ɂ��ẮA���ɂ������c�_����Ă���B���F�O���X���n�`�����l�� (2021)�ɂ����āA���Y�ۂ��吔�̖@���ɋt�炤���߂̐헪�Ƃ��āA(�C)���[�X�������炷�A(��)�w�����z�ɂ߂�͂������A(�n)�q����_�������Ȃ�����A(�j)���ɓq����Ȃǂ̕��@���Љ�Ă���B��O�n����ł́A����������A��ƌ����l���������邱�Ƃ�����B��z��S���[�X�ɓq����̂ł͂Ȃ��A�����鎩�M���傫�����[�X�ōw�����z�𑝂₷�l���悭��������B�ނ���吔�̖@�����ӎ����Ă��邩�͂��Ă����A���̉e�����Ȃ��悤�ɂ��Ă���Ɖ��߂ł���B���ɂ��A���̔����ɏo�Ă���w�����@�Ƃ͈قȂ�A�C�f�A��W�b�N�Ŕn�����w��������@�����邩������Ȃ��B����Ȃ̂ɃK�C�h���C�������Ȃ��Ɠ����Ƃ͌����Ȃ��ȂǂƖ{���Ɍ�����̂��낤���B��q�̒ʂ�A���n�͉ߋ��f�[�^���~�ς���Ă��āA�������{���ł���悤�ɂȂ��Ă���A������n���w���ɔ��f�ł��邩�Ȃ����ȃM�����u���ł���B�R�߂̎�(2)�ŃI�b�Y��p�������̎x�������`�������A�M�҂́A�I�b�Y���̓I����/������A�l�C�����̓I����/������A�n�Ԗ��̓I����/������ɒ��ڂ��邱�Ƃ�����BOhyama(2025b)�ł̃V�~�����[�V�����f�[�^�̌��ʂƓ��̒��ňÎZ����s����A�I������1�Ԑl�C��33%�A2�Ԑl�C��20%�A3�Ԑl�C��12%�A4�Ԑl�C��10%�A5�Ԑl�C��8%�A6�Ԑl�C��5%�A���̑���12%�Ɗȗ������ċL�����Ă���B�������6�Ԑl�C���炢�܂ł͑����̓ʉ��͂�����̂̂�������80%�ł���B�n�ԕʂł͋��n�ꖈ�ɂ���ẮA������̍����n�Ԃ����݂��邱�Ƃ�����B�M�҂͂����̐������Ȃ�ƂȂ��o���āA���[�X���Ƃɓ��I�ȉ~�O���t���C���[�W���Ă���B�Ⴆ�A�����������n��1�Ԑl�C���������Ă��鎞�A�g�����y�b�g�̃t�@���t�@�[�������Ă��鎞�_�ł́A�~��33%�����m����\���Ă���B�X�^�[�g���z��ȏ�ɂ悯��A���ꂪ50%�ɕω�����B�Ō�̒����ɓ����Ă����C�悭���������Ă���A50%����100%�ɉ~�O���t���ω����Ă����Ƃ�������B����ȃ}�j�A�b�N�Ȋy���ݕ��͐r������ȗႾ�Ǝv�����A�O�ꂽ�n���������n���Ƃ͖��W���Ƃ����̂́A�����̉~�O���t���C���[�W�ł�����ł͐������Ȃ��Ǝ咣�������ł���B
�{�e�͓���Ohyama(2025c)�̈�߂Ƃ��āA�p��Ō��J���邱�Ƃ��������Ă����B�������A�����i�߂邤���ɁA�b���ǂ�ǂ�c���ł��܂����̂ŁA��̘_���Ƃ��Ă܂Ƃ߂邱�Ƃɂ����B�O���Ɍ����Ĕ��M����K�v���͂Ȃ��ƍl���Ă���B�ނ���A�O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂Ȃ��Ƃ������Ƃ��O���ɃA�s�[������̂͏X�Ԃ��N�����ƂƓ�����������Ȃ��̂ŁA���{��ŏ������B�܂��A�{�e�͐R���t�̘_���ł͂Ȃ����A�����ȏo�ŎЂ�ʂ��Ă���킯�ł��Ȃ��B�w�p�I�Ș_���ɂ��邽�߂ɁA�����\�ɏo���Ȃ��Ƃ������Ƃ͂������Ȃ������B�����ł��������Ƃ��Ă��A�l���Ă��邱�Ƃ�����̂܂܃X�g���[�g�ɕ\���������Ǝv�����B�M�҂Ȃ�ɑ��p�I�Ȏ��_�ŁA�������Ă݂�����ł���B���n�Ɍ��炸�A���l�ɂƂ��Ċ����ȐŐ��͑��݂��Ȃ��B����͂킩���Ă���B�������A�Ⴆ�A�����ŁE���^�łɂ��Ă��A�@�l�łɂ��Ă��A�������ƌ����Ă�����@�͐�������Ă��Ă���A�����������߂��ƕ]�����Ă悢���낤�B�I�����x�ɂ����Ă��A��[�̊i���Ɋւ���c�_��ٔ������т��эs���A�������ւ̊S�̍������킩��B����ɑ��āA���n�Ɋւ��ẮA�\���R��̏�Ԃ̐l�̕��������A�ꕔ�̐l�������呹���A�����҂��������Ă���\���Ɖ��߂ł��Ă��܂���Ԃł���B�������A�����Ȃ芮���ȃV�X�e�����\�z����͖̂����ł��낤�B�܂��́A�Ŏ��������Ă��܂��̂͂قڊm�������A�O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂āA�Ŏ��A�\���R��̊������ǂ̒��x�ς�邩���m�F���Ă���A���̑���l����悭�Ȃ����Ǝv���B�O��n�����o��Ƃ��ĔF�߂�A�[�Ŏ҂͎��ۂɗ��v���o�Ă���킯�ŁA�����炭�\���R������邾�낤�B
�֘A�g�s�b�N���邢�͗]�k
�{�e�������O�́A�s�������₻�������V�X�e���E���@�ɒ��ڂ������͂��܂�Ȃ��������A�����ɂ��ĐG��邱�Ƃ��A�@�����Ƃł͏d�v�łȂ��̂��ƋC�Â����ꂽ�B���Ȃ�E�����邱�ƂɂȂ邪�����ɂ��āA�b�𑱂��邱�Ƃ������Ă������������B���n�Ɋ֘A�����j�Y�Ƃ����͔̂n���w���҂Ƃ��̊W�҂݂̂ɂ����e�����Ȃ��̂ŗD��x�͒Ⴂ�̂�������Ȃ��B����A���n�������̔ƍ߂͂���̂ł�͂�D��x�͍�����������Ȃ��B
��`�̕ۈ������Ȃǂ́A���т��є��������������āA���ł͌��d�Ȍ����������ɍs����悤�ɂȂ����ƌ����邾�낤�B�M�҂͓����悤�Ȃ��Ƃ𑼂̎�舵���ł��l���Ă��܂����Ƃ�����B���������{���͊��S�ɖh���悤�ɂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ����̂ł��邪�A�X�[�p�[��R���r�j�ɂ����ẮA���i�̒P�����������߁A�S���i�Ƀ^�O��t����Ƃ����悤�ȑ�͌����I�ɂ͌������B�����������Ă��܂��������Ƃ�����̂��d���Ȃ����A���݊e�Ђ��s���Ă���n���ȑ���p�����邵���Ȃ����낤�B����ŁA�����ԉ^�]���ށE�����̍w���A�����ƍ߂̑{���ɂ��Ă͂ǂ����낤���B���Ƌ��^�]����C�тщ^�]��{���ɂȂ������Ƃ���Ȃ�A�Ƌ���ǂݎ�点�Ȃ���G���W����������Ȃ��A�Z���t���̌ċC�����ɍ��i���Ȃ���G���W����������Ȃ��Ƃ����Ԃ�����A�����S�ȎЉ�ɂȂ�B��ށE�����̔̔��ɂ��Ă��A�����̌��N��{���ɍl����̂ł���A20�Έȏ�̔N��m�F���K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��A�������w�����Ă����v����t�����f���������}�C�i���o�[�J�[�h�������ɓo�^�����A�����ǂݍ��܂���ׂ��ł���B�A���R�[���ˑ��ǂ̐l���A���R�[�����Ă����ԂŁA�N����͍����̌��N�̂��߂Ƃ����̂͂��Ȃ薳���ȉ��߂�v�����Ă��邱�ƂɂȂ�B20�܂ł͌��N�ł��Ăق������A���������͎��ȐӔC�łƂ����̂��낤���B���łɌ����ƁA�M�҂͎������������łł���Ǝv���Ă��邪�A���N�Ɉ��e���Ȃ��̂ɂ��Ă͎�ށE�����ȊO�ɂ��Ă���������l����ׂ����낤�B�����͐l���ɂ�����邱�Ƃ����A���ɔ�ׂ�����̃V�X�e�������͈����̂ŁA�����Ƌc�_��i�߂Ăق����Ǝv�����Ƃł͂��邪�A�ǂ����ɓ��������c���Ă��������Ƃ������_���炷��ƁA�������������Ƃ͋c�_���ɂ����̂��낤�B�ԈႢ��R��̂Ȃ��d�g�݂��K�v�ȕ��̋ɂ݂Ƃ��ẮA�ƍߑ{�����������邾�낤�B���{�����̘b�ł͂Ȃ����A���E�Ǝv������m�F����Ă���̂Ɏ��E�Ƃ��ď������ꂽ��A�ʂȔƐl�����邱�Ƃ��z�肳���̂əl�ߎ����ɂȂ��Ă��܂�����A�����̏������W�܂��Ă��đ{������Ȃ������A�܂�ō�������邽�߂ɑ{�����I���ɂȂ������������т��ѕ���Ă���B���߂̐l���n�R�����Ƃ��ėL�߂ɂȂ�悤�ȁA�M�����u��������C�̂Ȃ��l�ɋ����I�ȃM�����u����������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ����悤�ɂ��Ăق����B�Ⴆ�A�ߗׂ̌x�@�g�D���{���A�؋��̊m�F���ł���悤�ɂ���Ƃ��A���̏������W�܂�đ{������Ƃ��A�l�̂�邱�Ƃɂ͊ԈႢ������Ƃ����O��Ő���������Nj����鐧�x���m�����Ăق����Ɗ�킸�ɂ͂����Ȃ��B���{�́A�����ȕ������Z�p����ɂ����������Z�p���]������Ă����B�����̋Z�p���@�����ɂ���������邱�Ƃ�Ɋ肤�B
�A�C���V���^�C���͐_�̓T�C�R����U��Ȃ��ƌ����Ă��邪�A���͐_�������̓T�C�R����U�邱�Ƃ�����Ǝv���Ă���h�ł���B���������������̂��A��Q�҂ɉߎ����Ȃ��ƌ�����悤�ȍЊQ�⎖���E���̂ł���B�M�҂͂��������������N����x�ɁA�s�ސT�Ȃ���A���̃��A�Ȋm�����A����������100���~�̔n�����Ă��鎞�ɋN����悩�����̂ɁE�E�E�Ȃǂƍl���Ă��܂��B�����⎖�̂ȂǂɊւ��ẮA�^�ɍ��E����Ȃ��悤�Ȏd�g�݂�Nj����ׂ��ł���B
�J���_�m�̓M�����u���[�ɂƂ��Ă̍őP��̓M�����u�������Ȃ����Ƃƌ����Ă��邪�A�i�ׂ�����킩��悤�ɁA���n�ɂ͕K���@������Ǝv����B�N�ł��^�p�ł���悤�Ȃ��̂��J��������������̂�ϑz����̂͊y�������Ƃł���B���n�ɂ���҂��d�������Ȃ��Ȃ�̂͏�ɔ߂������Ƃł���A�����Ȃ�Ȃ��悤�Ɋ肤�B�������A�V��2000���~���̂悤�ȈÂ��ۑ�͂Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�K���@������Ƃ킩���Ă���A���n�l���������āA���ɔ[�t����ŋ��������邾�낤�B�����̕K�v�����Ⴍ�Ȃ�A����A�w���ӎ������܂邾�낤�B�o�ς������z�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B���n���s�����̒ʉ݂�������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͂���̂��낤���B�����̉��l��������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͂��邾�낤���B�ǂ���ɂ��Ă��A�������Ŗ{���ɑ厖�Ȃ��̂͂����łȂ��Ƃ������Ƃ��ĔF�����邱�ƂɂȂ�̂��낤�B�n�����Ȃ��Ȃ�A���E�̕��a�Ɍq��������ȂƎv���B
���{�ł͏���ł̐ŗ��������c�_�ɂȂ��Ă���B�������A���������V�X�e���ŁA�ŋ��⋣�n�ƌ������L�[���[�h�Ō������Ă��A�����q�b�g���Ȃ�����ł���B���̐Ő��ɔ�ׂ�ƁA�w�p�I�Ȍ����͐[���Ȃ���ۂ����B���n�̐Ő��������Ɗ����ȋc�_���s���邱�ƁA����悭�A�����������ƍl���Ă�����@���A�O��n�����o��Ƃ��Ĉ����Ď��H�ł���������邱�Ƃ�����āA���тƂ������B
�Q�l����
JRA(�ŏI�X�V2025) ���ɔ[�t��ʂ����v��
https://www.jra.go.jp/company/social/treasury/
Ohyama T (2025b) Some Challenges for the Improvement of Doubling at a Virtual Racecourse
http://nirarebakun.com/hr/hrpaper.html
Ohyama T (2025c) A Suspicious Winning Method Using Constant Betting and Doubling at a Virtual Racecourse
http://nirarebakun.com/hr/index.html
Racing Post, Peter Scargill (2025�N5��20��) Betting tax increase would push British racing into serious decline and punters to the black market warns BHA.
https://www.jairs.jp/contents/w_news/2025/20/2.html
��c�@����(2015, ����27) �p���I�s�ׂƏ����̐�������Ƃ̊W�ɂ��ā|�C���^�[�l�b�g�𗘗p�������n�̔n���̕��ߋ��̉ېŊW�𒆐S�Ƃ��ā| �Ŗ���w�Z�_�p 81.
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/81/02/index.htm
��R�@��(2025a) ��R���̋��n���x�̃y�[�W
http://nirarebakun.com/hr/hrindex.html
��v�����@(2017, ����29�N)�@����29�N���Z������2�@���n���̕��ߋ��ɌW�鏊���ɑ���ېŏɂ���
https://report.jbaudit.go.jp/org/h29/2017-h29-0883-0.htm
���n�i�r(2024) ���n�̊Ҍ����𑍂܂Ƃ߁I�n���ʂ̍T�����⑼�M�����u���Ɛ��l���r
https://m-jockey.co.jp/keiba-navi/column/refund-rate/
���Œ��i�ŏI�X�V����30�N(2018)7���j�@���n�̔n���̕��ߋ��ɌW��ېłɂ���
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
���X�@���V (�ŏI�X�V2024) ���{�͐ŋ���肷���H���E�̐ŋ���r��N���ɂ�鍷���f�[�^�ʼn��
https://www.musashi-corporation.com/wealthhack/japan-tax
�������T�C�g(2024) ���v���̎g����
https://www.takarakuji-official.jp/about/proceeds/top.html
�ˉz ��O(2025) ���n�̉�����Ƃ́H���ς�v�Z���@��100%�����ɕK�v��7�̃R�c
https://m-jockey.co.jp/keiba-navi/column/recovery-rate/
�������H���T�[�`(2024) �ŐV�́u�Ԏ��@�l���v�A�ߋ��ŏ���64.8���ɒቺ�@�ŏ��͍��ꌧ�A�R���i�Ђ��n���Ǝ�̖��Õ�����
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198653_1527.html
���� ����(�ŏI�X�V2024) ���E�̑����ł͓��{��荂���H���{��e���̑����ŗ����Љ�
https://green-osaka.com/online/inheritance-tax/inheritance-tax-in-world
�����@�a�m�i�ŏI�X�V2013�N12��18���j�A�����J�ɂ�����n���ɑ���ېłɂ���
https://www.k-nakamura-law.jp/blog/?p=173
�����@�a�m�i�ŏI�X�V2013�N12��20���j�t�����X�ɂ�����n���ɑ���ېłɂ���
https://www.k-nakamura-law.jp/blog/?p=180
���{�d�ŗ��_�w��20���N�L�O�o�ŕҏW�ψ���(2012) �ŋ��S�����@�����o�ώ�
����@�Ԃ��� VISCAS(�ŏI�X�V2023) ���E�̏���ŗ��͂ǂ��Ȃ��Ă���H�����L���O������{�Ƃ̈Ⴂ�����
https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/money/78221/
���F�O���X���n�`�����l�� (2021) �g�[�N�e�[�}�́u�n���̔������v�I�n�����ǂ��������͋��n�t�@���i���̃e�[�}�ɁI���Y�� �h�V���~���F�O���X�I�u�n���͌��v�����L�O���C�u#3
https://www.youtube.com/watch?v=jUD_agfAVUw&t=6256s